私どもアンティーク買取えんやでは兵庫県小野市においてアンティーク、アンティークガラス、アンティーク陶磁器、アンティークドール、アンティークドレス、アンティーク時計、アンティークジュエリー、アンティーク家具、アンティークランプ、アメリカン雑貨、ファイヤーキングなどの買取・査定、鑑定を行っております。又、相続の中から出てきた遺品整理品、その他、引越、建替、実家整理などで出てきた処分してしまうにはもったいない不要品、不用品などの買取・査定も行っております。兵庫県小野市への出張買取はもちろん、店頭買取・持込買取、宅配買取も行っております。又、メール、ライン画像による簡単無料買取・査定も受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。
お持込買取の際は不在にしていることもございますので必ず事前のアポイントメントをお願い致します。また宅配買取の場合、発送前に一度ご連絡ください。発送時の注意点等お伝え事項がございます。
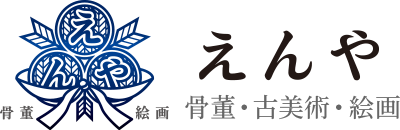
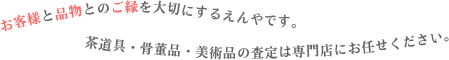


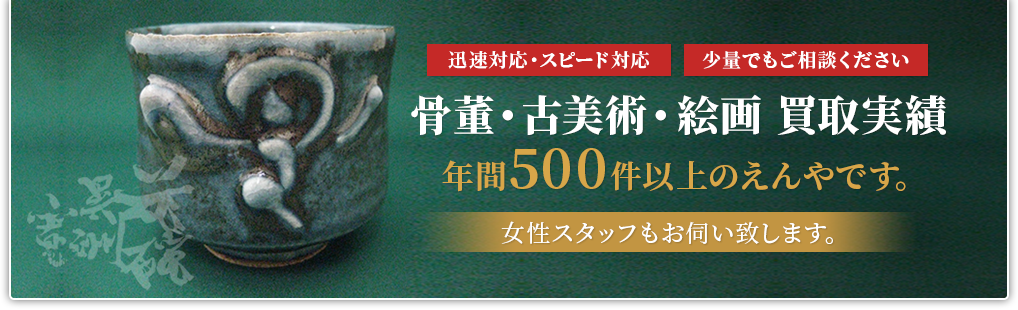










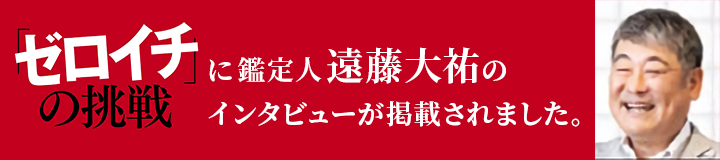 (PDF:909 KB)
(PDF:909 KB)




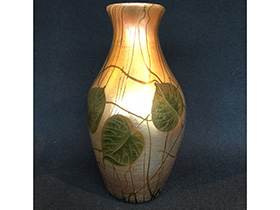












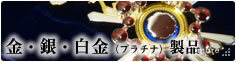
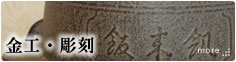


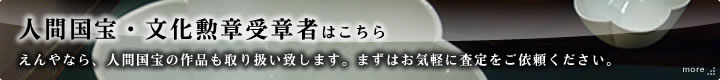
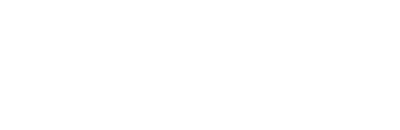
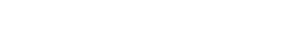



兵庫県小野市は約40万本のひまわり畑だったり、全長4kmの桜トンネルだったりと、自然を持ち味とした観光スポットが多くあります。また播磨エリア有数の牧場も主要観光地の1つで、近年はアンティーク感満載のイベントが人気のようです。2019年の初開催からまだ6回とキャリアこそ少ないものの、抜群のロケーションで年々、参加者が増加傾向の「播磨きららマルシェ」。
そのイベント名の如く、当日は輝かしいまでのアンティーク雑貨をはじめ、ハーバリウムやハンドメイドアクセサリーなどが会場を埋め尽くします。出店数は小野市内のアンティークショップや播磨地域の個人店など約30店舗と中規模ながら、ご当地グルメを満喫できたり、ワークショップで楽しめたりする各種プログラムが目白押し。また2021年の開催は3月を皮切りに、合計6回を予定しており、そのニーズの高さを伺わせます。それは同時に、小野市全体のアンティーク需要も上昇傾向にある、と言っても過言ではないでしょう。
アンティーク買取えんやでは小野市を対象とした、西洋アンティークの査定・鑑定・買取を実施しています。自慢の逸品を売却されるなら、ぜひアンティーク買取えんやに買取査定をご用命ください。小野市まで出張させていただき、買取いたします。
「現代ヨーロピアン」や「アメリカン」といわれる現代工芸品の買取も大歓迎です。陶磁器の有名どころではマイセンをはじめ、ヘレンドやセーブル、ロイヤルコペンハーゲン、ウェッジウッドが挙げられます。ガラスに関してはバカラやモーゼル、サンルイ、マイセンクリスタルなどが、人気の代表例です。カントリーグッズ、ファイヤーキングやアメリカン雑貨、一般的なブランド品・贈答品といった買取査定も行っております。
もし売却希望品の判断に迷うようでしたら「これは家のアンティーク」と思うものでも構いません。そのほか「美術館で見た」「百貨店で購入した」「海外土産」など、幅広いアンティーク作品に対応しております。早急に売却をご希望される場合は、その旨をお伝えください。精一杯の対応をさせていただきます。
扱うジャンルも、ガラス・陶磁器・ドール・レース・ブロンズ工芸品・銀製品・家具、と幅広いのがアンティーク買取えんやの強みです。
【ジャンル別の代表例】
ガラス:エミール・ガレ、ナンシー・ドーム、ルネ・ラリック、アルジー・ルソー、アルマリック・ワルター、オールドバカラ
陶磁器:オールドマイセン、KPM、オールドセーブル
ドール:ジュモー、ゴーチェ、ブリュ
家具:ガレ、マジョレル
ご自宅に眠っている作品など、譲り受けたお品物で置く場所や管理する場合など、遺品の行く末にお悩みの方でも構いませんので、アンティーク買取えんやにご相談ください。小野市のご自宅まで出張にて鑑定人がお伺いし、査定買取させていただきます。
【だからアンティークガラスは希少価値!】
アンティーク愛好家のなかには、バカラやスワロフスキーといった「クリスタルガラス」の世界に魅了される人も多くいます。そんなガラス製品は、アンティークの中でも陶磁器と肩を並べる人気ジャンルで、実は「西洋発祥の歴史」を持つところに価値があるのです。ちなみに西洋における、磁器生産の歴史は約300年。それに対してガラスは少なく見積もっても2000年、技術の発祥にいたっては4000年以上とされています。
地中海東岸のシリアやエジプトで、紀元前20世紀頃に製造が確認されているガラス。西暦1世紀には地中海を北上し、イタリアでローマングラスが誕生します。現代の主流でもある「鉄パイプによる吹きガラス製法」が確立されたのも、この時期です。いわばローマングラスがガラス生産の幕開けとなり、13世紀にはイタリア・ムラノ島で知られる「ヴェネツィアングラス」が登場するなど、より精度を高めていきます。
そんなローマングラス誕生の裏側には、陶磁器が大きく関係しています。ガラスは元来、陶磁器にも用いられる硅砂が原料のほか、双方ともに焼き上げる製法も一緒です。硅砂とは公園などにある天然の砂で、ガラスの主原料です。一方の陶磁器は、陶器も磁器も砂に、粘土と長石を加え原料としています。また陶器は粘土量のみが多く、磁器は砂と長石の量を増やして配合する違いも。製法については、
・ガラス→1700℃
・陶器→1000~1200℃
・磁器→1200~1300℃
と火加減で各々の硬度や強度を高めています。なお陶器は粘土量が多いため、水分を含むのが特徴です。それに対して磁器は粘土量の割合を減らし、より砂と長石の量を増やしている分、水分を含みません。ガラスには及ばないものの、高熱で焼き上げている点も、磁器が吸水性を持たないことに関係しています。つまり磁器は、よりガラスに近いセラミックなのです。
ではなぜ、ガラスが透明なのか?ここが陶磁器にはないガラスの値打ちで、矛盾でもあります。その理由は、ガラスには透明度を高める砂が多く含まれているからです。ちなみに、陶磁器を素焼きしたあとに施す「釉薬(うわぐすり)」の主成分も砂で、それによって“ガラス質”に仕上がります。いわば釉薬はコーティング機能をもって見た目に美を与えながら、陶器であれば水の染み込みを防いだり、磁器では劣化対策に一役買ったりなど、耐久性にも欠かせない存在です。
そんなガラスですが、実は陶磁器と同じ製法ではあるものの、真逆の工程をたどります。一般に陶磁器は轆轤や手びねりなどで形を整え、窯で焼成するのが主流の製法。ガラスも窯で加熱しますが、最初に原料を金型などに入れ一気に溶かした後に、吹き付けで形成していくのが主流です。そして陶磁器の釉薬を塗る工程と違う点が、よりガラスの透明度を高めています。これがガラス質と、ガラスの違いです。
一説には、マルコポーロによってヨーロッパに持ち込まれたとされる磁器。その製法を試みたのは、奇しくもローマングラスの発祥であるイタリアだったといわれています。しかし現地では磁器に適した粘土が採取できず、結局のところ陶器にとどまったのだとか。またその時代は、イタリアのヴェネツィアングラスに変わり、チェコのボヘミアガラスが台頭していった移行期。
その後、ドイツのマイセンが陶磁器の一時代を築くことになりますが、同時にガラス文化も元からの地場を生かし飛躍を遂げていきます。こうした過程を経て誕生していったのがマイセングラス、バカラクリスタルやスワロフスキーなど、現代を牽引する最高峰のガラスメーカーなのです。今を活躍するアンティークガラスは、まさに歴史と技術の集大成であり、その存在自体がプライスレスの域にあるといえるでしょう。
まずは買取専用フリーダイヤル0120-808-896またはメール、ライン画像による簡単無料買取・査定までお気軽にご連絡下さい。
勿論、兵庫県小野市以外でも近隣エリアにお住いの方であれば、お伺いできますのでお気軽にご連絡くださいませ。